初心者のみなさん、Webライターは文章書さえければいいよね?って思っていませんか?
仕事を受けたら、その日からプロ。ですから、単に文章が書ければいいと言う訳にはいきません。
じゃあ、Webライティング(=Web上で文章を書く)ってなに? なにが違うの?
そんな疑問にお答えするべく、実際に書きはじめる前に初心者が知っておくべきWebライティングの概要をまとめました。
必要な基本ルールとコツ、そして、記事の信頼度をあげるために必要なことを、現役編集者の視点で解説します!
 ま き
ま きこの記事では、知っておくべきことがひとつの記事でわかるように概要をまとめています。Webライティングの実践編(書き方)や、各項目の詳しい内容は、別記事にして今後順次アップしていくのでお待ちいただけるとうれしいです!



待っててね!
★この記事を読んでわかること
- Webライティングの7つの基本ルールとコツ。
- 記事の信頼度をあげるための知っておくべきこと。
Webライティング7つの基本ルールとコツ


では早速、7つの基本のルールとコツを解説していきましょう。
❶ 事実を書く
執筆にかかる前に、リサーチをしたり人から話を聞くことがあります。その際、そのまま文章にするのではなく、一旦、事実かどうかを確認することが必要です。
特に、Web上の情報は、不確実なことや嘘、フェイクが存在しているので、目にした情報を鵜呑みにせず、その情報の確実性を確かめましょう。
例えば……
- 自分で足を運んで確認できるのであれば見に行く、体験する。
- 専門家に話を聞く。
- 文献を読む。
- 物であれば使ってみる。食べ物であれば食べてみる
などなど。
万が一、嘘の情報を書いてしまうと、依頼主が読者の信頼を失ってしまいます。もちろんあなた自身の信用問題にもなってしまいます。



「~らしい」なんていうザックリとした表現はやめようね。



事実を書いた上で、あなた個人の感想を書くのは大丈夫ですよ!
❷ コピペはNG
ここで言う「コピペ」とは、他のサイトに書かれている意見や感想、体験などを、さも自分で取材し考えたことのようにそのまま書き写すこと。
NGの理由はいくつかあります。
- 著作権侵害になる場合がある。
- 著作権侵害になった場合、訴訟や損害賠償請求を受ける可能性も。
- 企業のWebサイトの場合、企業のブランドイメージが損なわれる。
- ライターとして依頼主や読者からの信頼を失う。
- Googleなどの検索エンジンの評価が低くなる(コピペしたコンテンツは順位が下がる)。
さらに、独自の視点や新しい情報がなく、他でも読める内容のため、読者にとって価値の低い記事となります。
あ! 今、「バレなきゃいいんじゃない?」って思った人いませんか?
確かに公開時にはバレないこともあるでしょう。でも、Web媒体というのは、いつまでもWeb上に残るという怖さもあります。それよりなにより自分のためになりません。
コピペに頼ってしまうと、リサーチ力やライティング力など、Webライターとしてのスキルが身につきませんよね。



自分の言葉で情報を発信しましょう!
あなたならではの視点や価値観があなたらしさになります。ひいては、あなたに仕事を依頼する理由になります。



だけど、引用の場合は“完璧にコピペするべし”。だよ!
❸ 読み手の視点を忘れずに
ライターの仕事は記事を読者に届けることなので、「読者が読みやすい記事」を目指すことが大切です。
ザッとまとめると
- 読者の年齢層、性別、初心者向けか詳しい人向けか、などターゲットを意識する。
- 完結に読みやすい文章を心がける。
- 読者の疑問や知りたいことに応える。
わかりやすくいくつか例をあげると
- 初心者向けなら専門用語を使わずに、わかりやすい表現を使う。
- 難しい漢字を多用しない。
- 一文を長く書かない。
などなど……。一番ダメなのは、
- 自分が書きたいこと、伝えたいことだけをだらだら書くこと。



Webライティングのコツは、リサーチなどの準備段階から、「この記事を読む人たちが一番知りたいことは何か」を考えておくこと。そうすれば、集める材料も書く内容も、読者に寄り添えるものになると思います。
❹ 構成を考えてから書く
リサーチや素材集めも終わり、いざ書くぞ!という段階になると、ついバーッと書き始めたくなるものですよね。
でも、ちょっと待って!
書き出す前に伝える順番を整理しましょう! その際、気をつけたいのが、記事の種類、ターゲット、文字量です。
ケースによって、書き出しの文章や構成、集めた材料のなにを使うかが変わってきます。
例えば……
●記事が店舗や物の紹介であれば、まず先に、店舗や物など対象物についての説明をすると何の記事なのかわかりやすいかと思います。
●記事の内容と文字量によっては、結論から先に書くPREP法を活用しながら結論を先に書くと構成がスッキリします。
★PREP法とは
- 文章をわかりやすくするための手法のこと。
- Point(要点・結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(再び要点・結論)の頭文字をとって「PREP法」と呼ばれています。
※詳しくは、別の記事でご紹介する予定なので、お待ちくださいね。
特に初心者の頃は、集めた材料をあれもこれも入れ込んで書きたくなるもの。そうならないように、執筆前に“なにを柱にしてどういう方向で書くか”、依頼主に伝えて相談すると良いと思います。
❺ 気をつけるべき3つの表現がある
日常会話の中で何気なく使っている言葉でも、発信するときには気をつけなければいけない表現があります。



ここでは、「略称」、「商標登録されている名称」、「差別につながる表現」の3つについて紹介するよ!
1. 略称について
「読者の認知度」、「略称そのものがOKかNGか」。この2つの点によって対応が変わってきます。
✔ 基本的には正式名称で書くのが望ましいですが、文中に何度も出てくる場合や認知度がある場合は、初出時に“正式名称+( )内に略称”と書くようにし、2回目以降は略称にしてもOKな場合が多いです。
例:労働組合(労組)
✔ 「SNS」「AI」などのように、この記事の読者はすでに知っていると思う場合は、そのまま使っても大丈夫でしょう。
✔ 「教科書」や「切手」などのように、略称がすでに名称として一般化しているものも大丈夫です。(※ちなみに、「教科書」の正式名称は「教科用図書」。「切手」の正式名称は「切符手形」です)。
なお、略称はNGで、常に正式名称で書かないとダメな場合もあります。
✔ 例えば、「東京ディズニーランド」。会話では、「ディズニー」、「ランド」、「TDL」など、いろいろな呼び名がされていますが、記事にする場合は、初出だけでなく、2回目以降も正式名称を書かなくてはなりません。
✔ 企業名や商品名などは、名称に中黒が入るか入らないか、ブランクは半角か全角かまで詳細に決まっているので、その通りに書く必要があります。



まだ駆け出しの頃、某外資系化粧品メーカー名のアキを、全角にしたことがありました。そのとき、メーカーさんから「半角アキにしてください」と言われたことは忘れられないです。。。



とはいえ、初心者の頃はわからないと思うし、依頼主によっても考え方・ルールが違うので、遠慮せずに依頼主に教えてもらおう!
2. 商標登録されている商品名
日常会話の中で、「宅急便」、「タッパー」、「バンドエイド」など、代名詞として口にすることはありませんか?
「宅急便、送っておいて」
「残ったらタッパーに入れて」
「バンドエイド取って」
などなど。つい言っちゃいますよね……。でも、実はこれら、公の文章で使ってはいけないんです。なぜなら、商標登録されている商品名だから。
- 「宅急便」は、“ヤマト運輸株式会社が提供している宅配便サービスの商品名”のこと。
ゆえに、使用するときは「宅配便」が正解!
同じような理由により、
- 「タッパー」は「プラスチック製の密閉容器」
- 「バンドエイド」は「絆創膏」
と書きましょう! あ、「カットバン」も商標登録されていますよ~。
……というわけで、商品名にはご用心!
3. 差別につながる表現
この解説については、具体的に記述しにくいのですが、性別、職業、身分、地位、信条、人種、地域、身体的特徴などに関する差別的な言葉や言い回し、差別と取られるような表現は気をつけなければなりません。
東京都江戸川区が、差別的表現を避けるためにガイドラインを策定しているのを見つけましたので、目を通してみると「こういうことか」……と参考になるかと思います
下記のページから、東京都江戸川区「男女共同参画の視点に立った表現ガイドライン」のPDFを見ることができます。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e090/kurashi/jinken/sankaku/hyogenguideline.html
❻ 一貫性を持たせる・3つのポイント
Webライティングの一貫性について気をつけなければならないのは、やはり記事の信頼度のため。
「文体」、「表記」、「内容」の3つの点から見ていきましょう。
1.「文体」について
- 「だ・である」調で書いていたのに、途中から「です・ます」調になるなど、文末を混在しない。
- カジュアル、ビジネスなど、各記事のターゲットに適した文体に気をつけ、混在しない。
これらのことが混在していると文章のトーンが揃わないので、統一するようにしましょう。
2. 「表記」について
- 数字(算用数字の半角、算用数字の全角、漢字)、マーク(円か¥など)統一する。
- ひとつの記事の同じ単語は、平仮名、カタカナ、漢字、英字(大文字か小文字)など、統一する。
例えば、「Webライター」と書く場合、「WEBライター」「ウェブライター」とも書けますよね。どれでもOKですが、どれかひとつに決めましょう。
3. 「内容」について
- 導入部分と結論が違うなど、感想や意見、データが矛盾しないようにする。
- 書いているうちに伝えたいことがずれていかないように、テーマに沿った内容に。
一貫したメッセージを伝えることが大切なんです。



これら3つのポイントを意識すれば、読みやすく、信頼性のある記事を書くことができます!



企業によっては、サイト内全体で文体や表記が決められていることもあるので、そのときは合わせよう!
❼ SEO(検索エンジン最適化)を意識する
依頼主に求められた場合、SEOは意識するべき重要な要素となります。
SEOを意識した記事を書く。それは、Googleなどの検索エンジンに評価されやすくなるということ。
すると、読者が検索したときに上位に表示される可能性が高くなり、より多くの読者に記事を届けることができるようになるのです。
では、SEOを意識するとはどういうこと?というわけですが、特に大切な2つのポイントをあげると、
- 検索されやすいキーワードをリサーチし、タイトル、見出し、本文にキーワードを自然な形で入れ込む。
- 見出しを適切に使うなど、読みやすい文章構成を意識する。
です。初心者の方にはなんのこっちゃかと思いますが、SEOを意識して記事を書くことは、読者にとっても価値のある記事となりますし、仕事の幅も広がると思うので、おいおい学んでいきましょう。



SEOについては、今後、別の記事で詳しく解説する予定なので、お待ちくださいね。
Webライティングの信頼度のために


Webライティングは、ライティング力だけでなく、Webライターとしての信頼度も浮き彫りになってしまいます。
そこで、初心者でも「おっ、信頼できるかも」と思ってもらえるように、意識したいことを解説します。
- 誇張した表現は避ける/大げさな表現や、読者をあおるような文章は避けましょう。
- 引用元を明記する/文献やほかのサイトなどから引用した場合は、うやむやにせずに必ず引用元を記載しましょう。引用元を記載しないと著作権を侵害したと思われてしまう可能性があるかもしれません。
- 校正・修正に手を抜かない/提出する前には必ず自分で読み直し、誤字脱字や文脈などのチェックを怠らないように。そして、依頼主より修正が入ったら真摯に対応しましょう。
Webライティングとは関係ないのですが、Webライターとして信頼してもらうためには、社会人としてのマナーを守ることも大事なことだとつけ加えておきます。



納期を守る、メールには返信する、あいさつをする、遅刻をしないなど、社会人としてのマナーやルールを守ることも忘れないでくださいね。
まとめ
Webライティングってなに? なにが違うの?
この記事では、初心者のうちから知っておくべきWebライティングの「基本ルールとコツ、」そして、「記事の信頼度をあげるために」の概要を現役編集者の視点で解説しました。
こうやってまとめてしまうと、気をつけることばかりで、ライティングどころじゃない!っと思うかもしれません。
ですが、誰しも数をこなしていくうちに自然と身につくことなので、表現や文体については最初からパーフェクトにこなそうと思わずに、まず書いてみて、読み直してリライトする……ぐらいの気持ちでトライしましょう!



では、またほかの記事で会おうね~!
「Webライターに求められること」を書いているこちらの記事(↓)もチェックしてね!



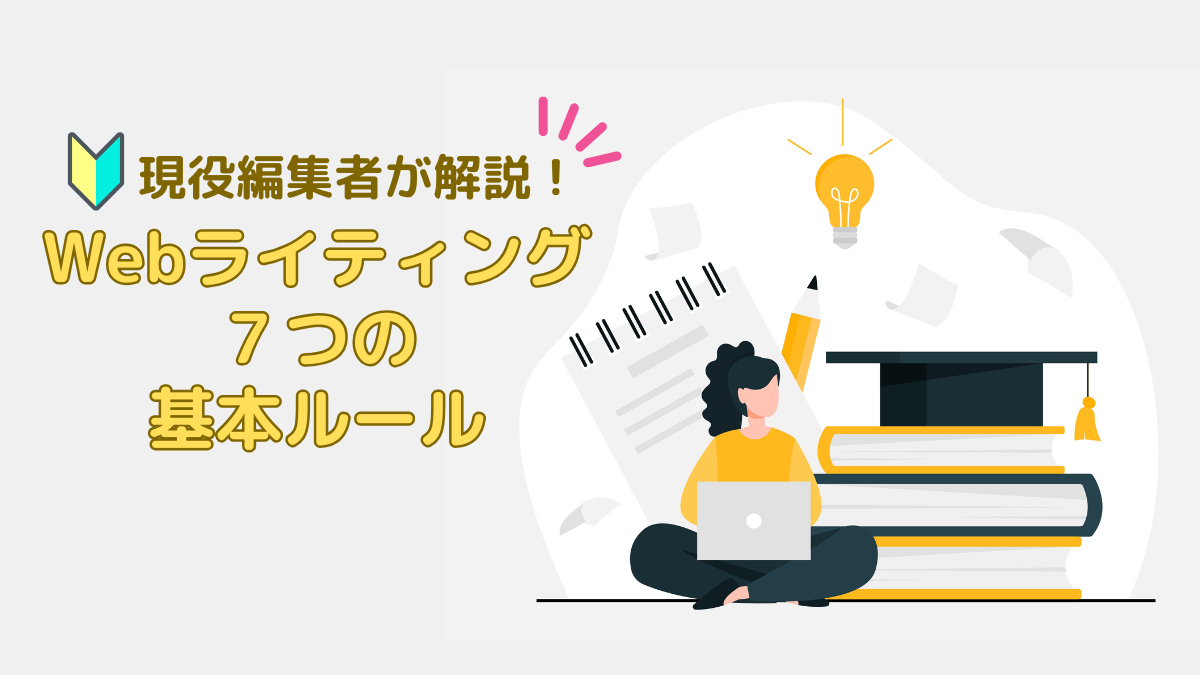
コメント